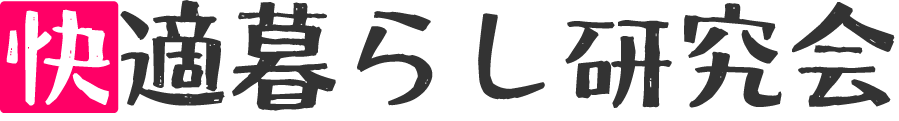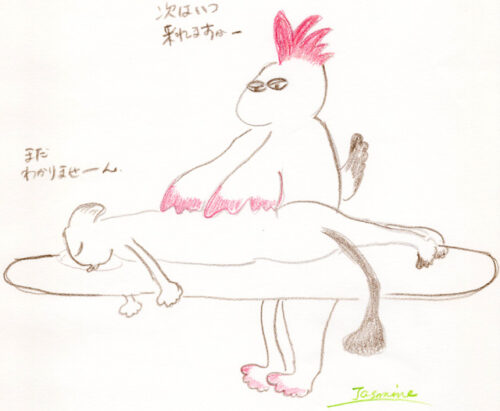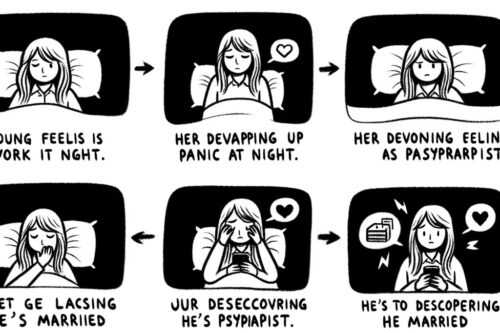右がデンちゃん(オス)、左がミーちゃん(メス)※撮影は筆者
学生時代、映画『タクシードライバー』頃のロバート・デ・ニーロ似の先輩がいた。女性にはよくモテた。その先輩が言った。
「オスが浮気をするのは、種を残すためで、遺伝子レベルでそのようなつくりになっているからだ。リチャード・ドーキンスという遺伝子学者も、そう書いている」。
『虹の解体―いかにして科学は驚異への扉を開いたか』というタイトルの本を懐から出した。水戸黄門が葵の印篭を差し出すように。
先輩の仕事は戦場フォトグラファーであった。ジャングルに潜む反政府ゲリラを取材中、日本から女性がジャングルまで追いかけてきたこともある。モテ逸話にこと欠かない。そんなモテ先輩が説くものだから、珍妙な「リチャード・ドーキンスの世界」を長い間、信じていた。

右がデンちゃん(オス)、左がミーちゃん(メス)※撮影は筆者
当然ながら、周囲には、先輩の話で説明がつかないオスたちもいる。誠実なオスたちだ。たとえば、近隣住民から溺愛されている地域ネコのデンちゃんも。彼は、ミーちゃんというメス猫以外に関心を示さない。私もデンちゃんにならい愛妻家だ。デンちゃんや私は、オスとは言えないのだろうか?
先日、主著『利己的な遺伝子 < 増補新装版>』を1か月ほどかけてしっかり読んでみた。ドーキンスの世界観は、先輩の話ほど単純ではなかった。
進化的に安定な作戦と言えるなら、オスに浮気をさせる戦略の遺伝子は残ってゆくだろう。しかし、戦略もさまざままだ。
浮気っぽいオスが増えれば、メス側にも不誠実さを見抜く必要が生まれる。形勢は逆転し、浮気っぽさこそは、淘汰される要因なる。これでは「雄が浮気をしないのは、遺伝子がそうさせているから」という説明になりかねない。

ドーキンは、むしろ「オスが」とか「オレは」とか「民族は」とか「〜の国民は」とかいった、群的な淘汰を批判する。
デンちゃんとミーちゃんのように、お互いに恩恵を与えあい、安心する気持ちを獲得した2匹もいる。先輩のように「オスは浮気をするものなのだ」と断言するのは正しくない。