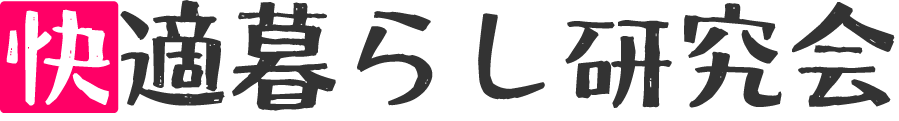イラスト:モクソン ホウ
妻の足裏を揉むたびに、私は谷崎潤一郎の短編小説『刺青』を思い浮かべます。これは、彫物師と妖婦の艶っぽい物語です。
あらすじ
清吉は、浮世絵師くずれの彫物師。彼が彫る刺青は、構図が美しいと評判でした。清吉は仕事を選ぶ男で、気に入った体と肌を持つ者にしかほどこしません。それでも望まれるなら、ブラックジャックの外科手術のように、高額な料金で応じるのでした。
清吉にはサディスティックな一面がありました。彫物をほどこしたあとの耐え難い苦痛でうめく客を見て、心地良さを感じているのです。「さぞお痛みでがしょうなあ」と言って、薄ら笑いを浮かべるのでした。
ある日、清吉は、娘が乗る駕籠(かご)からこぼれる美しい足を目撃します。この美しい足の持ち主こそは、求めていた女だと確信しました。この娘を捜し続けた四年目の夏。偶然、清吉のもとへ小娘がつかいにやってきます。清吉は、この娘こそが、捜し求めていた女と直観します。
「顔を見るのは始めてだが、お前の足にはおぼえがある」と言って招き入れます。娘に、生け贄の男を眺める絵や、男たちの屍骸を眺める女を描いた絵を見せます。 「この絵にはお前の心が映って居るぞ」とか「この絵の女はお前なのだ。この女の血がお前の体に交って居る筈だ」と言って、淫靡に責めます。はじめは怖がっていた娘でしたが、やがて「私はお前さんのお察し通り、其の絵の女のような性分を持って居ますのさ」と言って、妖婦の素質をちら見せるのでした。
清吉は、この娘に麻酔薬をかがせます。そして、一昼夜をかけて、背中に女郎蜘蛛を彫ります。娘が目覚めると、それまでのか弱い乙女ではなく、男を「肥料」(こやし)にする妖婦の高慢さが生まれていました。
感想
「刺青」は、1910(明治43)年11月に雑誌「新思潮」で発表されました。谷崎潤一郎の実質的な処女作です。明治時代の作品なのに、現代の文章としても違和感がありません。
「すべて美しい者は強者であり、醜い者は弱者であった」 という一文は、この物語の思想を端的に表しています。
清吉は仕事を選べるほどの売れっ子です。浮世絵師くづれの経歴も箔を付けたことは想像に難くありません。清吉は業界のエリートであり、仕事を選べるほどのセレブであり、強者なわけです。
四年間も女を捜し続ける清吉の行いは、まさしくストーカーです。嫌がる娘を家に招き入れ、麻酔薬をかがせるあたりは、もはや犯罪です。しかも、眠っているすきに、彫物までします。あきらかに一線を越えています。後ろめたい世界をのぞき見するようで、ドキドキしてきます。
可憐だった小娘の背中には、見事な女郎蜘蛛の入れ墨がほどこされます。娘から妖婦へと変貌し、清吉は女のためなら喜んで命を投げ出す「肥料」になってしまいます。物語の雰囲気は、交尾のあとメスがオスを食べてしまう女郎蜘蛛そのものです。食肉された訳ではありません。清吉に強者の姿はなく、妖婦の前にひれ伏す弱者と化したのでした。
清吉の姿は、東京帝国大学を中退し、文章を書くのは余技だと言い切る秀才の谷崎に、どこかしら重なる気もしました。
家族サービスで妻の足裏を揉むときに、清吉と同じ感覚に陥ることがあります。妻が「いたぎも!」と悲鳴を上げるたび「さぞお痛みでがしょうなあ」と言って薄ら笑いを浮かべてしまうのです。妻の血色はますます良くなり、元気いっぱいです。