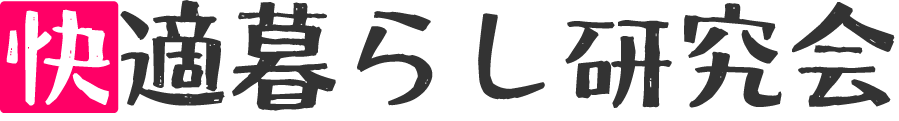石焼ビビンパ(菜彩 五反田店)写真:筆者
根本的なところに立ち返れば、いったい石焼きビビンバとは本来どのような味なのだろう。ボイルしたブロッコリーを前に思索した。しかし、本物の石焼きビビンバの味は実際に食べてみなければ分からない。
私が作る「石焼きビビンバ」は独自の進化を遂げていた。まるでオーストラリアの動物だった。
ブロッコリー、大根の葉っぱ、トマト、がんもどき、しそ昆布、笹かまぼこ、焼き肉のタレ……。冷蔵庫にあったものを石鍋の飯の上に乗せる。ガスコンロの上に置き、真ん中に生卵を落とした。ほのかに「杜(もり)の都」の味がした。もはや韓国料理ではなく、東北地方の多国籍料理である。生卵が真ん中にあるおかげで、石焼きビビンバに見えた。タブレットの裏側にリンゴのマークがあるだけで、それがiPadに見える理屈に似ている。
小林克也がラジオから流れるFEN(極東放送網)で英語を勉強したように、現地に行かなくても、YouTubeで本場の味は学べると私は信じていた。モンテーニュも言っている。「人は異なる手段で、同じような目的に到達する」。道は違っても、すでに同じところにたどり着いている可能性もある。そうだ、これはすでに石焼きビビンバの可能性がある、と。これでは「可能性」で説明する二流のコールセンターだ。
そんなことを言っている私を見て、妻は気の毒そうな顔をした。妻は食通である。とっくの昔、韓国料理店で石焼きビビンバを食べた経験がある。妻は経験に基づきこう言った。「石焼ビビンバにブロッコリー🥦 がんもどきは合わないと思う……」。がーん。
妻に誘(いざな)われ、プロが作る石焼きビビンバをついに食べることになった。東京の五反田駅近くにある「韓の旬 菜彩 (ハンノシュンサイサイ)」という韓国料理のお店だ。レミィ五反田8階にある。

目的地はレミィ五反田8階
時間はランチタイム。メニューには「石焼きビビンバ」「プルコギビビンバ」「チーズビビンバ」「伝統のビビンバ」……と並ぶ。若い女性店員が注文を聞きにやってきた。ここはためらうことなく、「石焼きビビンバ」を選んだ。5〜10分後、注文の品が運ばれてきた。

菜彩 五反田店の「石焼きビビンバ」
プロが作った本物を目の前にして感無量だった。女性店員に「この黒いのは何ですか、この白いのは?」と聞いた。「黒いのはゼンマイで、白いのはゴボウです」と店員は答えた。
緑色は小松菜かホウレンソウ。モヤシ、細切り卵、ひき肉、そしてレタスのようなものも見える。五味五色の具材をコチュジャンと生卵の黄身がしっかりとまとめている。まるでレッドツェッペリンを束ねるジョン・ボーナムのドラムとジョン・ポール・ジョーンズのベースような仕事ぶりに思われた。

まぜて現れるお焦げも楽しみの一つ
私が作る「石焼きビビンバ」とは何かが違っていた。焼き肉のタレかコチュジャンかという違いだけではない。何かが加わっている。トウバンジャンかもしれない。コチュジャンとは、もはや何かと何かが混ぜられた独特のソースに他ならなかった。深く、まろやかな味だった。感動的だった。この深さは何なのだろう。どのように言い表せばよいのだろう。味が分かるどころか、むしろ謎が深まってしまった。味の決め手はコチュジャンだということはなんとなく分かった。味を知るこの旅はまだ始まったばかりのようだ。(写真も筆者)

清潔感のある店内でランチを楽しめた