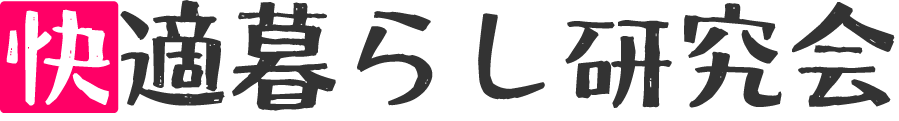不惑の四十になってしまったが、時をおり人生を振り返る。若かりし日に出会った人たちは、いまでも元気だろうか。そんなとき、荻原魚雷さんの本が読みたくなってしまう。魚雷さんの描く時代と風景には、見覚えがある。
荻原魚雷さんは「本の雑誌」などで活躍する文筆家 [1]だ。著書の袖には、控えめなプロフィールがある。
1969年三重県生まれ。文筆家。大学在学中からフリーライターの仕事をはじめるも、なかなか生計がたてられず、アルバイトで食いつなぎ、現在にいたる。
2010年に刊行された本書『活字と自活』の装丁は、漫画家山川直人さんのイラストを使っている。本書の内容はタイトルのとおりで、活字中毒の筆者が愛蔵書を紹介しつつ、文化的な生活のこだわりと自活の苦悩を綴る。「自活」には、自立とか自律といった「インディペンデント」の含みがあるのかもしれない。世俗から距離を置く人生は不安定である。だが、その危うさこそが、本書の魅力になっている。
魚雷さんの雰囲気は、山川直人さんの漫画にでてくる主人公の男の子に似ている。山川直人さんのキーワードが「コーヒー」だとすれば、荻原魚雷さんは「古書」ということになるだろう。これらを切り口に、人生の辛酸をむしろ味わい深いものとして語るのだ。
ところで、1990年代のはじめから半ばまで、私は高円寺に住んでいた。手前味噌だが、魚雷さんの住むアパートにお邪魔したことがある。閑静な場所にあって、わび住まいに相応しい古いアパートだった。そこには、まさしく『活字と自活』で見えるような本棚があった。
20代の魚雷さんは若い仲間たちと、こたつを囲み、文学から思想哲学まで語り合う。魚雷さんは、デビューしたての町田康に似た、鋭さと優しさをあわせ持つ目をしていた。面倒見も良く、周囲には若手たちが集まっていた。
すでにライターとして活躍しており、私にも「モクソン君も大学なんて辞めて、社会に飛び込むべきだよ」なんて言う。私は魚雷さんのクールなまなざしから生まれる言葉が大好きであった。
数年経ち、魚雷さんとお目にかかる機会はなくなってしまった。噂で、別のアパートに引越したと聞いた。なんでも「ネズミがでるので、もうここには住めない」というのが理由らしかったが、真偽のほどは分からなかった。ところが『活字と自活』を紐解くと、このネズミの話があるではないか。
壁がうすくて、ネズミが出るアパートから引っ越したかった。電話が止められてしまうような生活から抜け出したかった。ワープロ、カメラ、テープレコーダー、FAXなど、この先フリーライターを続けていく上で必要な仕事道具を買いそろえたかった。
出典:『活字と自活』,本の雑誌社, p29
ひょんなことからブラックジャーナリズムの世界に身を置いていた時代の逸話である。魚雷さんは、労働条件が最悪の職場に違和感を持ちつつ、仕事を頑張っている。その理由は、ネズミがでるアパートから引っ越しをしたかったからだという。この最悪な仕事を終えてから、中野界隈に向かう描写が続く。この風景は、私も見覚えがある。
そのころ昼は仕事、夜はだめ連のメンバーと遊んでいた。彼らのアジトは、中野と高円寺のちょうどあいだくらいにあった。中野駅前の駐輪場ではよく酒盛りをした。
出典:『活字と自活』,本の雑誌社, p29
いまでは、中野駅前の駐輪場で酒盛りはできない街作りになってしまったが、1990年代は少々違った。全国から若いアーティストや学者のタマゴたちや、ヌードモデル、編集者、政治活動家、学生、フリーターといった人たちがここに集まり、有象無象の様相を呈していた。今思えば、あれはあれで良い時代であった。
本書の語り口は、おおむね静かである。「部屋を掃除して洗濯して食料品を買い物して古本屋をまわって喫茶店で本を読んで酒を飲んで家に帰る」といった具合に、質素でつつましやかな生活が描かれている。その一方で、趣を有す人生であっても、生活費を稼がねばならぬシビアな課題もある。そこで綴られる苦労や心配事も、本書を読み解く上での面白さであり、魅力なのだ。
気がつけば、私たちは人生の折り返し地点までやってきた。苦労も良きネタに思えるようになったのは、一つの成長なのだろう。